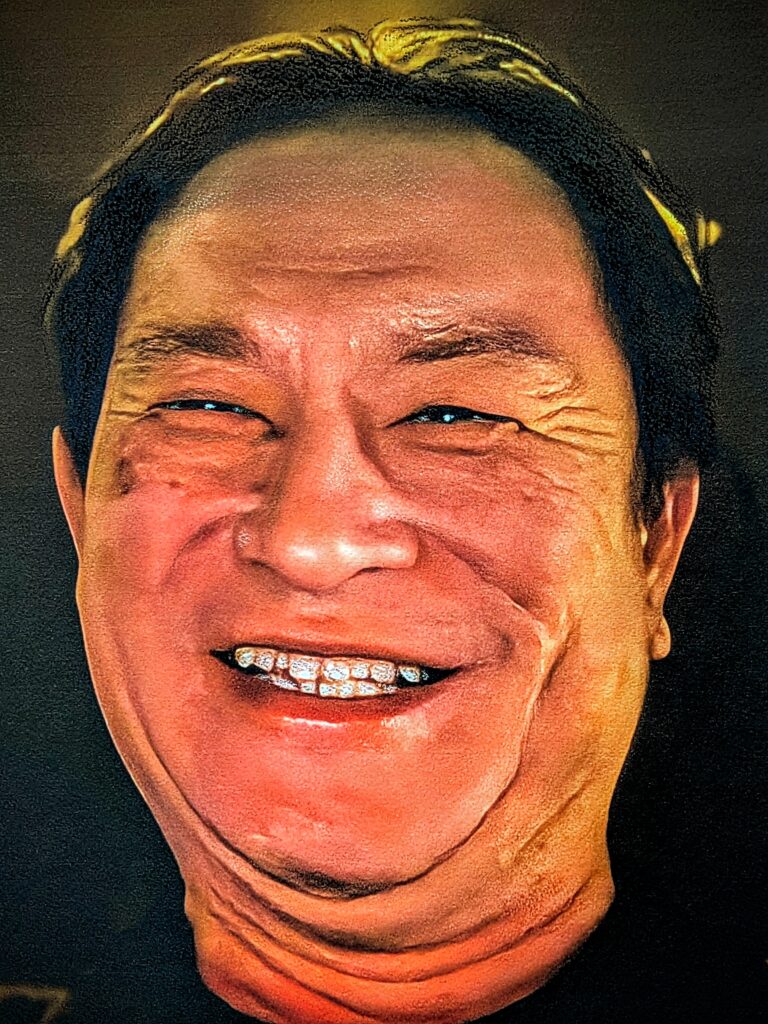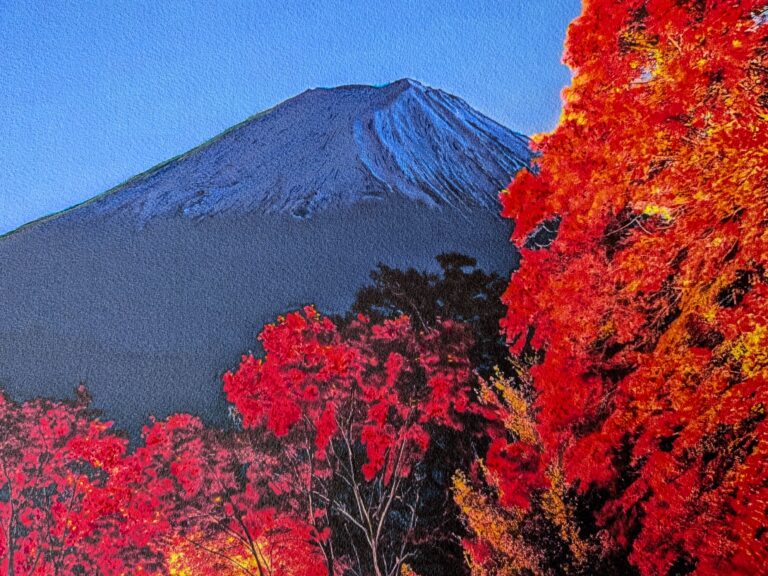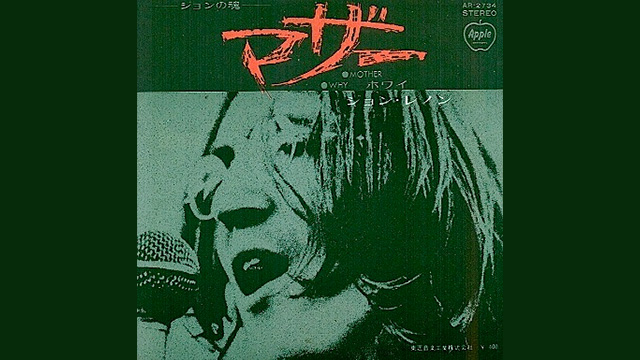ノンフィクション小説「かもめのDNA」第1話「クリエイティブの未来、それを語るステージに、リクルートがとっくにいない件」
物語を始める前、まず最初に。 ここに登場する人物の名は全て実名でありしかも敬称略であることを、ご了承いただきたい。 まあノンフィクション「小説」であるから、企業名も登場人物も仮名で進めるのが良いし、そうすればそんなことわりは必要ないのだろうが。ただ、実名であることに意味があることがあまりに多いこの物語は、実名にて書いていくことに決めた次第である。実名を操ることを決めた最大の理由は、この物語の完結は […]