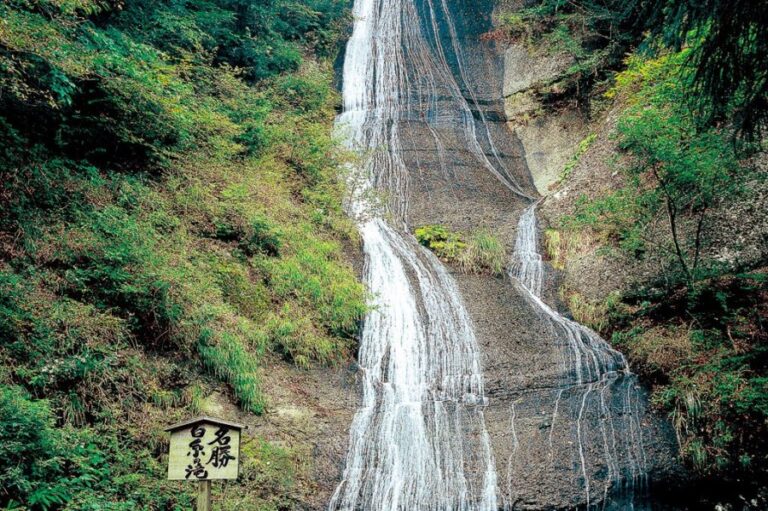水鳥の大群を夜襲と勘違いして敗走した平氏が見ていた同じ景色を、道の駅「富士川楽座」から(トイレ◎仮眠✖️休憩○景観◎食事○設備○立地○)
「富士川の瀬々の岩越す水よりも早くも落つる伊勢平氏かな」(鴨 長明『方丈記』)長明は、東西の雌雄を決する戦いとなった「源平富士川の合戦」を日本三大急流富士川に見立てて、平氏方の敗走ぶりをこう詠んだ。1180年10月20日夜、甲斐源氏武田信義一隊が動いたのに驚いた水鳥の大群が、一斉に飛び立った。平氏方侍大将上総守忠清の先陣はこれを夜襲と勘違いし、鎧をすてて京に逃げ帰った、その様である。 ここ富士川町 […]