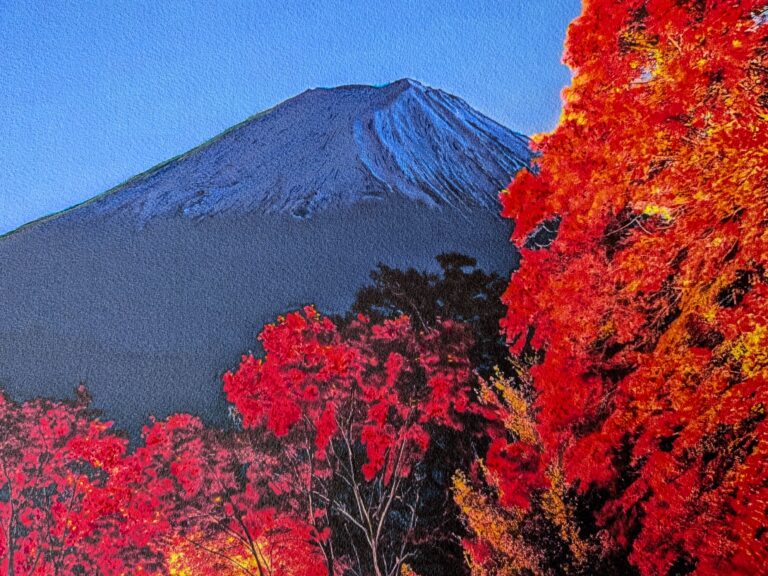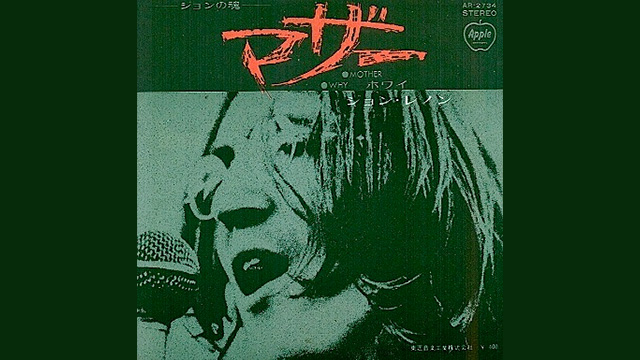23作目の顔は、どうしても笑わない。笑顔の君が、どうしても描けない。「越生さん、悔しいですよ」って。大好きなお前がそう言ってるんだよ。嗚呼、池辺!
池辺正博くんとの出会いはかれこれ40年前に遡る。当時まだ駆け出しの営業マンだった彼が、制作課長になったばかりの私のデスクにやってきて、こう言った。 「私、池辺正博といいます。実は日立造船さんを担当することになりまして、日本のビッグビジネスにご参画いただけることになったのですが、ご存知のようにもう原稿締め切りは過ぎているのに書いてくれるライターさんが見つからず、掲載をお断りしなければなりません。どう […]