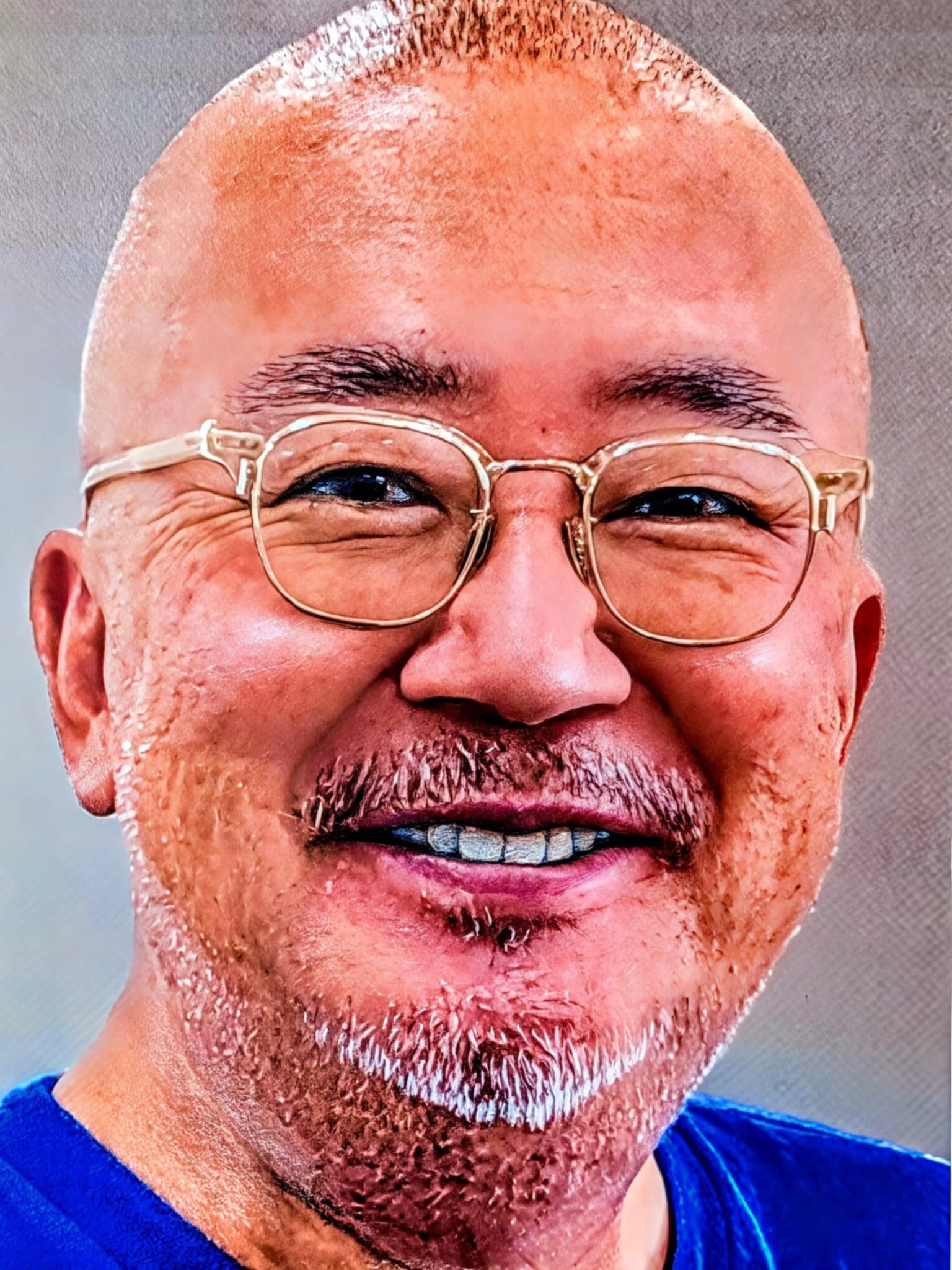
この第4話には何が書かれているかを最初に一言で言うと、それは「リクルートのクリエイティブ残酷物語、その序章である」ということになる。
残酷物語が始まったのは、リクルート創業から10年、1970年のことであり、その終焉は1997年。私の一番弟子でありリクルート制作のエースに成長した絹谷公伸の電通への「放出」によって、足掛け27年に及んだ残酷物語のすべては、「リクルートクリエイティブの完全消滅」という形で終わった。
序章として描くのは、27年間続く残酷物語の前半にあたる、1984年までの14年間。それは、リクルートが社会や学生が「広告の塊」を「情報&出版」と大きく錯覚していた時代に粛々と繰り返された、人材採用と放出をひたすら繰り返した歴史である。
それは、少し長いスパンで冷静に観察してみると、人材の「輩出」などといった綺麗事では決してなかった。
間違いなく「排出」と言う漢字が当たっており、なんなら「放出」にも近い行為の繰り返しだった。
少なくとも江副リクルート、位田リクルートの時代において、「光」は営業部門、「影」は制作部門であり、その暗い影の、はっきりとは見にくいところで、制作人材の獲得と放出は日常茶飯事として繰り替えされていたのだった。
「リクルートだけはダメだ」と、すでに日本の各芸術系大学は学生を送り込むことをやめているが、リクルートは制作、クリエイティブなど全く必要としない会社にとっくに変身していて何ら困らない。
リクルートは、さんざん日本の芸術系大学の人材を使い捨てにし続けてカスカスにしてから、まんまと次のステージ(現在の新しいリクルート)へと駆け上がったのだった。
リクルートクリエイティブの悲劇、その幕開け
1960年に創業してしばらくの間のリクルートの事業は、「大学新聞」〜「企業への招待」のみ。
65年にはその高校生版を、68年にはのちに83年にリクルート映像として独立する映画事業を始めた程度で、その頃はまだ「情報出版」などといった錯覚は、少なくとも学生側にはなかったと思う。
ところが70年代最初の入社者であり第2話に登場した馬場マコトには「電通、博報堂と似たようなもの」という珍しい錯覚があった。彼は第一志望の広告代理店、電通、博報堂への入社が叶わず、「似たような」と錯覚してリクルート(当時は日本リクルートセンター)に入社した。
江副はこの馬場マコトがあまりに文章表現者として優秀だったため特別扱いし、コピーライターとして仕事をさせた。しかしそんな彼にして、学生に送り届ける自社媒体の原稿を書く仕事には「クリエイティブ」のカケラも見出すことができず、馬場マコトはたった2年でリクルートを後にしている。
そんな馬場先輩より断然、数倍アホな私だが、彼の失敗から12年、受かるかどうかは別にしてうちの大学からは先輩筋から上げて貰えば最終選考には必ず進めた、その電通、博報堂を、私はどちらも受けていない。
受けずに「なんだかリクルートって電博より面白そう、女性はイケイケだし、中でも受付の岡本さっちゃんは抜群だし」という動機で、私はリクルートを選んだのだった。
申し上げるに恥ずかしいそんな理由だが、少し詳しく話しておきたい。
一つ目、最大の理由は、70年に入ってぐんぐん加速した「リクルート=かつてない情報出版」というイメージに惹かれてしまったことだった。
イケイケの女性従業員たちのイキイキ感にやられて
リクルートは創業から10年後、まず70年に「リクルート進学ブック」を、75年に「就職情報」、76年には「住宅情報」を創刊していた。
80年の「とらばーゆ」創刊のインパクトは女子学生には破壊的に大きく、この頃には「新興情報出版企業」としての一定の注目を、「出版」をキーワードに就活を進める層の学生から集めるようになっていた。
しかし住宅情報にしても就職情報、とらばーゆにしても。
所詮、全ては「情報誌」の皮を被った「広告の塊」であった(でしかなかった)。
この、いわゆる出版、あるいはマスコミなどとは全く異なる性質の「どぶ板営業」から成り立つ「広告屋」と言う本質が、学生の私にはわからなかった。
理屈をわかったところで、結局やってみなければわからなかったのだが。
いざ配属されてみて仕事を始めると、クリエイティブ発揮の範囲の乏しさに気づく。
それはクリエイティブに燃える我々のような人種には忙しさなどよりずっとキツく、もっとも辛いことだった。
仕事を始めてそのことにやっと気づくが、「リクルートに行きまーす、お世話になりま〜す」と言って内定してしまう時には、全くわかっていない。
何だかわからないがぼんやりと「電通や博報堂やテレビ局より面白いことができそう」などと信じていたことは、今思えば実に愚かなことであった。
要するに、私でなくても、電博、出版、マスコミなどとの、それぞれの決定的な違いというものに自ら気づくほど、当時の私たちは利口ではなかった。学生運動に燃えた団塊の世代からも「三無主義」などとバカにされた私たちの世代の、世間知らずの学生は、あまりにも己の人生に無頓着、要するにバカであったのだ。
81年の銀座G8ビルの竣工、大阪では新大阪駅前のリクルートビルも、新幹線に乗ったこともなければ綺麗なガラス張りのビルになど入ったこともない田舎者の学生を騙すのには一役も二役も買った。
急成長の象徴のようなビルは、私を惹きつけた二つ目の理由となった。
そして男にとってのダメ押しは、イケイケの女性従業員たちのイキイキ感だった。これが、私が電通や白鵬堂を受けずしてリクルートに飛び込んだ3つ目の理由である。
いや、私とは全く別の意味で、女子学生にとってのダメ押しもまた「それ」すなわち「イケイケの女性従業員たちのイキイキ感」だったのではないだろうか。
制作志望の学生を騙すことほど簡単なものはなかったろう
私が当時天秤にかけていた会社の女子従業員は、ほぼ全員が製造工程の工員の制服姿だった。
わずかにいた事務職の女性も、自前の服が汚れないように両腕に黒い事務用肘当て?をつけておられた。受付には人がいらっしゃったかどうか、お会いする女性はみんな「飴ちゃん、やろか?」と今にも聞いてきそうな大阪のおばちゃんばかりだった。
かたや、リクルート大阪ビルの1階受付には、私が一目惚れした岡本さっちゃんという美人がいた(柴田教夫というR82同期に速攻で奪われノーチャンスだったのだが)。
アルバイトしていた期間は毎日、そして面接でリクルートを訪問する機会には、さっちゃんの顔を見れることが楽しみになった。
アテが外れて、違う女性受付にいることもあったが、ガッカリ感は少なかった。
なぜなら、みな、若くてピチピチ(今こんなことを言ったらセクハラ?)と美しく、当時のOL(笑)ファッション最先端のスーツ風ユニフォームに身を包み、私の目を見つめてにっこり微笑むのだ。
普段の芸大生活で、一緒に酒を飲みつつ同じ部屋で徹夜で絵を描く仲間、女子学生の友達は多かったが、スカートを履いたり化粧などしているものは皆無。みな、化粧の代わりに顔には飛び散った絵の具、着ている服もまた絵の具まみれのツナギ、徹夜明けで腫れた目にはヤニなんか溜まっちゃっててw。
そんな友人女性を見慣れた目から、さっちゃんを見たら濁ったウロコがポロリ、そりゃあね、あーた。
「ほ、惚れてまうやろ〜!」
大阪をちっぽけなものとして見下ろして
最後の理由、4つ目は採用担当者のかっこよさだった。
リクルートに入ることを約束する儀式としてS.H.=シェイクハンドというものが存在するが、私にそれをしてくれた相手は富永兼司である。
S.H.の場所は、大阪市街を一望できる高層ビル最上階のレストランだった。
私はもう、初めて見下す大都会、大阪の夜景にキョロキョロしながらも、出される酒、それはビール、ワイン、ウイスキーなどだったが、それらを手当たり次第に一気に飲み干しおかわりを重ねながら、コース料理にがっついた。
当時、学生時代の私の主食は、王将でただ食いできる餃子10人前と、それ以外はパンの耳であり、この時コース料理に出されるものは、それまで見たことも食べたこともない食べ物ばかりであった。
私が大好きな酒も、学生の身分では手がでなかったものばかり。ただ豚に真珠も勿体無い、ということで、「次はこのあたりはどう?」と富永に勧められるまま、ワンランクだけ上の、今になって思えばごく普通の銘柄限定(笑)で、それを何杯も飲んだ。
学生時代の4年間を通じて、酒はビール、焼酎はさつま白波、日本酒は剣菱、ウイスキーはトリスかレッドか、最高級でホワイトだった。そして、ワインなど飲んだことはなかった。ワインなんて赤いのと白いのがあるぐらいしか知らぬ、それが酒かどうかもわからない私であったから、S.H.で飲み放題させていただいたワインの美味さに私の目が赤白、もとい白黒したのは当然で、その滑稽な姿に笑いを堪えられず、富永兼司はずっと笑っていたのだろう。
いろんな酒を飲み続け、皿まで舐めるように平らげていく私を、何も言わずにただ笑って見ておられた彼は、店の勘定をカードで払った後に私を連れて店を出て、エレベータが最上階に上がってくるまでの間、夜景を二人で眺めながらの時間をとってくれた。
そして、こう言った。
「ちまちまと人が蠢いているけど、ここからは全部、見える。リクルートの情報がずいぶん社会を変えているよね」と。
「こ、この人、カッコいい!」
私がそんな感情で彼を見つめると、彼はやおら私の手をとって、「じゃあ、頑張ってね」と強く握ったのだった。
制作殺すにゃ刃物は要らぬ、木に蜜塗っておけば良い
彼の名誉のために言っておくが、富永兼司は私を騙してはいない。
彼とS.H.するまでの1ヶ月、夏休みのうち1ヶ月間まるまる、リクルート大阪支社の広告事業制作部門でアルバイトし、私は現場を知った上で自ら志望したからだ。
毎日岡本さっちゃんの顔を見るのが楽しみだったし、また、職場のイケイケのおねいさんたちに命令される快感に私のM感覚は打ち震えながら、毎日絶頂寸前気分で私はアルバイトに通い続けた。
実は、ミズノでも1ヶ月間アルバイトをやった。そして母校・明石高校での教育実習期間もちゃんとこなしたし、スポーツ用品のミズノ、高校美術教師の道も悪くなかった。
ではなぜリクルートに決めたのか。
それは岡本さっちゃんの笑顔、イケイケの先輩女性、これに対抗できる魅力が、リクルート以外の2つの道にはまるでなかったのだ。
結局、私にとって「岡本さっちゃん」は、カブトムシ捕獲のために木に塗りつけられた蜜であり、私はそれに惹きつけられていとも簡単に捕らえられたカブトムシに過ぎなかった。
こうして私はリクルートに入社することを自ら望んだわけだが、その82年には、街中に「フロムA」創刊のティーザー広告が溢れ、CMが垂れ流され始めた。
「ほら、あれを見ろよ」
と「だましのしまだ」率いる人開スタッフ。
制作志望の人間を殺すにゃ刃物はいらぬ。フロムエーのCMを見せりゃいい。
ついには木に蜜を塗るまでもなく、口説くトークも要らないように。
ポスターやビルの上の看板広告を「ほらな!」と指差すだけでこと足りるようになった、そんな気がした。
「かっこいいな」「新しいな」「これからもまだまだ新しいものを作っていくのだろうな」
などと、「つくること」が好きで、その魅力に興味を持った若造を騙すことなど、赤子の手をひねるようなものだったろう。
情報の中身にまるで関心のない美大デザイン系
リクルートは84年には、学生にも親しみが持てる海外旅行情報誌「AB-ROAD」、中古車情報誌「カーセンサー」を相次いで発刊。本屋でもリクルート印(かもめ)の情報誌が目立つようになっていく。それは依然、広告の塊でしかないのだが。それでも出版に関心がある学生の、リクルートに対するイメージはどんどん高まっていった。
というのは、私は京芸ビジュアルデザイン科の学生だったが、本屋に行く目的は本を買うことではない。買った本は「ゴルゴ13」のみ。
今どんなデザインが受けているのかを勉強しにいくことだけが目的だった。
本屋では、本の装丁、雑誌なら表紙しか見ない。
かっこいいデザイン、新しいロゴなどを探して、イケているものを見つけると、どこがイけているのか考えるのだ。私はコピーにも興味があったから、雑誌なら表紙のタイトルの出し方や、貼られてあるポスターのキャッチやボディコピーなどを読んで、いいものを見つけると、インスパイアされた。
「俺ならもっとかっこいい表紙を創ってやる」「よし、もっとイカしたコピーを書いてやる」「このロゴは、もっとこうした方がいいな」と、関心事はそれだけ。
だから、中身をほぼ捲らない。その雑誌が広告の塊であろうがなかろうが、そんなことは関心がなかった。
まさか自分がその一コマひとコマ、1ページ1ページの広告を千切っては作り、作っては投げる千本ノックの毎日を送ることになろうとは、そこには鶏飼育場的働き方が待っているわけだが、入社を待つ間もずっと、そんなことは考えたこともなかったのである。
すでに一定の「制作枠」も採用する時代になっていたが、人開にしてみれば、デザイン系からの採用はこんな程度のやつを相手にするわけで。
採用レベルを年々上げることが彼らの使命であり、だから売れる即戦力の営業人材を採用することのハードルは決して下がることはなくても、制作を採用することなどは朝飯前なことだったろう。
少なくともリクルート制作残酷物語が芸術大学内で話題になり始める1985 年あたりまでは。
1982年当時の、リクルート・クリエイティブの景色
では実際に、R82の私が、入社直後に実際に見た「リクルート制作の景色」はどうだったのか。
まず東京では、圧倒的知性で真っ先に強烈に憧れを抱いた江原文子、のちの上司・網野千文の両名に、新進気鋭の千葉望。3人の女性が輝いていた。
そして、デザイナーとしての大迫修三、クリエイター然とした大嶽一省、二人とは対照的に文章の達人としての中澤等(さかな)の仕事が私の興味をひいた。
私のデスク周り、つまり配属された大阪では、東京から異動してきた仕事人・中嶋康博、鬼ディレクターの故・吉田由美子、ブレーン・コピーライターの橋本正治が頭抜けていた。
他にも、何十人もの先輩社員の名前ぐらいは覚えているし、GA、A職の中にむしろクリエイティブがキラリと輝く人はいたが、いつの間にか居なくなっていた(笑)
先輩の人数だけは東京、大阪の他にも全国各地にもたくさんいらっしゃったが、私が「クリエイティブだな」と思った先輩たちは今名前をあげた、たった9人だけだった。
ちなみに同期同輩にクリエイティブな人間は皆無。後輩に、永遠のライバル長薗安浩、デザイン力際立つ柏本郷司、私の一番弟子でTCC最高新人賞に浴した絹谷公伸、自分でA職採用して育てた二番弟子・三枝義浩、ビジネスもできる黒田真行、映像にも強いアートディレクター近藤昭彦、我が道を行く作家いしいしんじ、全くリクルートには順応できなかった大学後輩(する必要もなかったが)天才・田原幸浩の8人がいる。
その後、もちろん育成する役割から後輩たちには常に目を配ったが、クリエイティブを感じない多くの先輩たちの仕事には、生意気ながら全く興味を持てなかった。
ここに名前をあげた彼ら彼女ら17人は、能力的にも実力も実績も申し分のないすごい先輩であり後輩だったから、リクルートを「やめても食っていけた人」ばかりだが、それだけに、別の言い方をすれば「進む道を間違えた人」たちと言えるかもしれない。
「失礼なことを言うな、俺は私は道を誤ったつもりはないよ」とおっしゃる人がいたとしても、リクルートにおいては「クリエイティブ」と言うものが重要視されないという不遇は、一様にあった。
制作の仕事に携わっていた人間は「元リク」「卒業」という言葉を使わない
だから「こんなはずじゃなかった」と制作に失望し、あるいはこき使われて疲れ果て、あるいは心身のどこかを悪くしてリクルートを去る人間は後を絶たなかった。
どんな仕事をしていたかを問わず、リクルートを辞めた人を一律に「元リク」と呼ぶが、その中にはこんな人が一定数いる。
「元リクはすごいね」「リクルートって人材輩出企業だよね」などと言われるのが心地よいと思える人だ。こう言う人たちは自分のことを「リクルートを卒業した」と言って、自己アピールに余念がないが、私が「誰に卒業証書もらったん?」と質問すると、一瞬きょとんとした後、黙ってしまう人たちである。
まあ人間はディスられるより褒められるのが好きだから、何も知らない人間から「元リクってすごいよね」などと、そう言われるままにそんなもんかな?と思っている人も多いのかもしれない。
しかし、少なくとも「制作」と言う職種を深く体験した人たちの中には、中澤さかな、絹谷公伸、柏本郷司、黒田真行など次のステージで大成功した人たちを含め、「元リク」「卒業」と言う言葉を軽々に使う人はいない。
それは、制作の仕事をしたことの、いいことも、それ以上の良くなかったことも、「元リク」「卒業」と言う単語が想起させる概念とはまったくしっくりこないからに違いない。
もっとはっきり言っておこう。
一握りの一部例外を除けば、「輩出」などと言う美談ではない、さんざん使われての使い捨ての悲劇を間近でたくさん目撃し、体に不調をきたし矢折れ刀尽き気力失せた友人たちが、組織からボロ雑巾のように「排出」されてきた残酷物語の歴史の、その証人でもあるからだ。
悪い噂が広まるより早かった成長スピードも相まって
美大デザイン系の人間で「長居」をした人間は少ないが、でも彼らが大学に戻って被害者然としてリクルートの「悪口」を言ったかというと、そんなものは人によるわけであるし、言ったところでだ。
「あなた、たった●年で辞めちゃって、要するに通用しなかったのね」
なんて思われたら、癪なだけではないか。
美大デザイン系の人間は、もともと自分の「腕」「感覚」に自信がある。リクルートとの体質、相性が悪かったことは、実は彼らの腕を傷つけたわけではないので、さほど傷つかずにあっさり辞める人が多い。また、ジェントルな人も多い。
営業の人間に比べて「声が小さい」のだ。
私のように歯に衣着せず思ったことを、しかも大声で、人の悪口さえ言うような輩は突然変異的で例外中の例外、美大生にはほぼいないのである(笑)。
だから、である。
「悪い噂」が広がるスピードは遅かった。そして、それよりもはるかに猛烈なスピードで成長するリクルート。美大デザイン系からもどんどん新しい血を吸い取り続けて、制作の悲劇?は、毎年のように続いていくのだった。
おそらく1970年の中頃から80年代のバブルの入口ごろまでの少なくとも10年間、リクルートの「制作」に関心を持った人の多くは、リクルートが新興の「情報出版会社」で、その目覚ましい成長を「クリエイティブな会社」だと錯覚していたに違いない(笑)。
だから彼らの最も多い退職パターンは、「思った感じじゃなかった」ことによる。
これは大変幸せな、退職パターンとしては最高のものだ。
だって、失望した、という程度である。傷は浅い!(笑)
芸術系大学からの入社の始まりと終わり
芸術系大学からのリクルート入社、その端緒はおそらく76年に多摩美術大学グラフィックデザイン科から入社した大迫修三ではなかっただろうか。
次に、武蔵野美術大学、日芸(日本大学芸術学部)、公立では金沢美術工芸大学、愛知県芸術大学あたりが続いたようだが。
京都市立芸大からリクルートに入社したのは私の1年先輩R81の林弘幸が最初。R82の私、そして4年空いてR87の田原幸治の3人だ。皆、己がリクルートに「クリエイティブ」と言う幻想を抱いたが、私以外の二人はそのことに気づくや否や、1年ほどであっさり辞めて行った。私はかろうじてコピー系だったので残る意味もあったが、辞めた二人はガチガチのデザイン系、長居をする理由などこれっぽっちもなかった。
結局、私だけが9年半粘って(笑)、その私もリクルートを去ったが、この3人の「犠牲」を糧に、後にも先にも、京都市立芸術大学からリクルートを志望する者は皆無となった(笑)
これは何も私の出身大学に限ったことでもなく、また、他の芸術系大学にも同様のことが起こったが、それは、所詮芸大、大したことはないやで済まされる、そんな特殊で小さな話ではなかった。
なぜなら、「あそこだけはやめておけ」と「定評」は、さすがに半世紀以上も経つとおそらくほぼ全ての芸術系大学に浸透したからであった。
おそらく芸大系では、尊敬する中嶋康博や写真のプロ秋吉らを送り込んだ日芸こと日本大学芸術学部、林弘幸、私、田原幸浩を送り込んだ京都市立芸術大学、伊波正春、柏本郷司らを送り込んだ金沢美術工芸大学、三浦基嘉らを送り込んだ愛知県立芸術大学、大迫修造ら比較的多くのデザイン系卒業生をリクルートに送り込んだ多摩美術大学、武田均ら常軌を逸した破天荒人材が多い武蔵野美術大学、といった日本を代表する美術系大学からのリクルート入社は、1980年代以降、ほぼ絶えて久しいはずである。
これらは日本のトップ芸術大学と言って良いだろうが、そこからはただ一つ、この残酷物語に学生を誰一人巻き込まれたなかった大学がある。
日本の最高峰、東京芸術大学だ。
6浪7浪当たり前、芸術を追求するために全国から集まってくるこの学府の牙城は、いかにリクルート人開が凄くても崩せなかったに違いない。
そして、日本芸術界の宝たちを守った教授並びに進路指導スタッフには敬意を表してやまない。
リクルートに行くのはいいが、ただし「制作」はダメだ
芸大デザイン系だけが使い捨ての話の中にいたのではない。
たとえば新人時代、私が憧れた江原文子の母校は、東大だ。
私の息子は彼女の後輩で、中高時代から写真や文芸にのめり込んでいたので、リクルートだけはダメだぞと念の為に繰り返し刷り込んでいた。
そんなことを言わなくても時代は変わって「制作」なんて仕事はリクルートにはとうになくなっているというのが笑えてしまうオチだが。
「クリエイティブをやりたければ博報堂がいいんじゃないか」と。
ちなみに娘は遺伝か何かわからないがマーケティングコンサル、人材系企業にこだわったので、「リクルートもありだけど、ちょっと難しすぎて無理だろうと言うと、今や超難関、R86辻本秀幸率いるヴァリューズを受けて玉砕(笑)、のちパーソルに採用していただいて、もう6年以上そこで頑張っている。
東大、慶應、早稲田、京大…。
日本のいわゆる偏差値上位大学から多くの先輩がリクルートの制作、クリエイティブに何かを期待して入ってきては、辞めていった、まさかそんなことを最愛の娘や息子ににまで体験させれば、もう親としてアホなのである。
「時代が変わった」で済むのは今の話。リクルートは、「リクルートの制作だけは絶対にあかん」とOBの私に言わせるような残酷物語を、序章として今ここに書いている84年までの14年間だけでなく、それ以降もさらに10年以上、繰り返し続けたのだ。
そんな中でもっとも長く制作畑で、残酷物語の一部始終を間近で見つつ、最長不倒勤務を続けた人物はおそらく、網野千文である。
制作以外にも営業なりスタッフなりも器用にこなせるタイプの一握りの人材以外、「リクルートの制作」の実情を知ってしまえば、先輩たちも私も後輩たちもそうだったが、非常に長くもって10年。それが限界だったろう。
短い人は1年、普通で3年、まあまあ長居して5年ほどで、みんな辞めていった。
そして、それを問題にした社長、役員を、誰一人として私は知らない。
私は第二話で「なぜ社内のクリエイターにリクルートのCMを制作する機会を与えないのか」と憤ったが、江副はまだ古き良きリクルートの創業10年目には馬場マコトの才能を見出しており、決してクリエイティブ音痴な人ではなかったと思うが、何しろ事業拡大に忙殺され、早くも70年代には不動産と株取引に夢中になって、80年代の最後、事件発覚直前に位田尚隆に社長のバトンを渡す頃には、クリエイティブなどはとうに彼の眼中になくなっていた。
いや、馬場マコトを手放した1972年には、江副にクリエイティブへの想いなどもうなかったのかもしれない。
リクルートを一時的とはいえクリエイティブな会社にした男、現る
そんなリクルートというクリエイティブ不毛な会社に、遅まきながら1980年代の中盤になって、正面きってクリエイティブの火をつけようとした人間が現れる。
その人は、もちろん江副社長、バトンを受けた位田社長でもない。
ましてや当時広告事業のトップであった河野栄子でもない。
当時のどこかの事業部の役員のリーダーシップでもなければ、やはり、制作畑で比較的長く頑張ってきた諸先輩方の、誰でもなかった。
まず、事業トップの河野栄子は、麻雀の鬼であることがそれを象徴しているが、勝つこと以外に興味なし、売り上げと利益しか頭の中に存在しない人である。
渡邉嘉子というクリエイティブを大切にした女性はいたが、同じ女性ではあっても、河野栄子はオバはんの皮を被ったおっさん(失礼)。のちにリクルート借金完済に必要となるコストカットの鬼となって大活躍されたが、そういう人に全く理解できないクリエイティブを大切にしてほしいと思う方がどだい間違っているのである。
そして、制作畑の諸先輩に期待することもまた大間違いである。
制作畑に長居しているうちに、原稿制作は上手くなっても人を動かしたり仕組みを変えたりする力は削がれていく。いや、正しくは。インテリだけれどあまりにも「そういう力」が欠落していることが、政策畑で長居できる唯一無二の資質なのである。
全事業部門の制作畑を見渡しても、もはやそういう人ばかりしか残っていなかった。
そんな人たちに何を期待できようか。
だからこそ。その人は突然、思いもよらないところから現れたのだった。
関一郎がいなければ、私の仕事に陽が当たることはなかった
皮肉なことに、リクルートにクリエイティブの火を灯そうとし、それを強力に推進した人物とは、入社以来伝説の営業マンであり続け、営業マン史上間違いなく累計売上最高を誇るであろう、その実力と実績をもってして当時のリクルートの大黒柱であった広告事業全体の営業を率いるようになった、リクルート営業のエース、関一郎だった。
あの藤原和博がライバルと公言するなど、伝説の営業マンとして社内で知らないものはいない関一郎だったが、80年代に東京の大手企業と長きにわたって太く強いパイプを築き、リクルート事件の頃には広告事業(現在のHR)全体を率いる立場にのし上がっていた。
彼によってリクルートのクリエイティブがにわかに盛り上がり始めたその時期は、江副が株ばら撒きを行った84年から85年にかけて。まさにこの頃と期を一にする。
社内評価に過ぎなくても、「アドコン(アドコンテスト)」が立ち上がり、制作に携わるものの評価基準が、初めて数値化され、明確になったのだった。のちにリクルート全体の「人事」をも掌握する関一郎にしては、そんなことは朝飯前のことだったかもしれない。
もとより営業は、数字が全て。営業数字、達成率で、明確に評価されていた。
しかし、彼らが売ってきた広告ページをバトンを受けて制作するものは「受け身」でしかなく、「よくやっている」「期待以下だな」「ミスが多い」「遅刻が多いな」ひどい場合は「覇気がない」など、上司の「印象による評価」しかなされていなかった。
それを、制作の人間に対しても明確な評価基準を設けることに着手した関一郎のお陰で、私は1985年、1986年と連続してアドコンのベスト5(2位、4位)に入り、制作ページ数はトップ。
つまり今盛り上がっている冬季五輪で言えば、ジャンプ(瞬発力=質)とクロスカントリー(距離=量)の合計点数で競うノルディック複合(コンバインド)での連続メダルのような、「通期優秀制作マン賞」を、マネジャーになる前、2年連続で受賞したのだった。
関一郎の先見性と、私のパツパツ。それも光と影の好対照か
私観ではあるが、彼の凄さは、営業の拡大に制作クリエイティブが大いに寄与できる、そしてその可能性は、企業の採用意欲をたきつければ無限とも言える、そんな確信を持ったことにこそあると思う。
ただリクルートブックを凡庸に企業情報を収納するだけでよしとすれば、そこで企業ニーズも「その程度」に収まってしまう。
時代はバブル。
より自由で奔放で制限のない表現ができる媒体設計をして、クリエイティブによって企業と学生とのコミュニケーションはどこまでも拡大できる、新たなニーズが生まれる、彼はきっとそう考えたのだと思う。
彼は、営業部門のトップであることに加え、制作部門のトップも兼務した。
そして、営業出身なら営業偏重だろう、という周囲の凡庸な見方を見事に裏切った彼が、リクルートの制作にクリエイティブの火を点火したのだった。
その手腕は実に見事なものだった。
営業と制作クリエイティブの化学反応、次元増床、スパイラル効果のトリプル進化を狙い、思い描いた通り(以上かも)にことを運んでみせた。
リクルートの制作に関わる社員、A職だけではない。
さらにはブレーンさんに対しては、クリエイティブを存分に発揮し、それを評価し合える場、いただいた貢献に報いる場、具体的には「クリスタルコンテスト」を新設した。
また、「求人広告半世紀」を編纂し、求人広告というもののジャンルを考察し、「市民権」を持たせ、制作に関わるクリエイターが誇りを持って邁進できる環境をつくろうともした。
そんな1988年4月1日、私はと言えば、それまでの半年間上司平尾勇司に高い評価をいただき、マネジャーに昇進。関西広告事業全体の制作を率いることになった。
私は、新たに再編成された関西広告事業部に最適な制作体制を構築すべく、関西 拠点に散っていた大阪エリアの企画制作機能を大阪支社に集結させた。この新体制を、当時「一括」と呼んだ。
そして、一括にしてしまうと効率が落ちるであろう大阪圏から距離的に離れた神戸と姫路、京都と京都南には、力のあるリーダー、具体的には神戸姫路に絹谷を、京都京都南には亀山を配した。
こうしてなんとかかんとか関西の制作部門全体を指揮できる体制を整えていった最中、1988年の梅雨が始まろうとしていた頃だった。
東京や関西はもちろん、日本全国の現場に寝耳に水の、とんでもないことが起こり始めていた。

