
出羽三山とは、山形県の中央にそびえる月山(1984m)・羽黒山(414m)・湯殿山(1500m)の総称で、1400年以上前に蜂子皇子によって開かれ、祖先の霊魂、山の神・海の神が鎮まる山として古くから信仰を集めてきた。
西の伊勢神宮に対し、出羽三山に詣でることを「東の奥参り」として人生儀礼の一つとする風習があるほどの、日本屈指の修験道の霊山だ。
「三山」といっても独立した三つの山があるわけでなく、月山を主峰に、峰続きの北の端に羽黒山があり、月山の西方には湯殿山が、峰続きに並んでいる。
羽黒山が現世(正観世音菩薩=観音浄土=現在)、月山が前世(阿弥陀如来=阿弥陀浄土=来世)、湯殿山が来世(大日如来=寂光浄土=未来)という三世の浄土を表すとして、羽黒山→月山→湯殿山の順に巡礼するのが一般的。現世の羽黒山から入って、月山で死とよみがえりの修行を行い、湯殿山で再生する巡礼は、生まれ変わり(死と再生)の意味をもった「三関三渡(さんかんさんど)」の旅とされている。

山岳信仰
日本列島においては古くから、山や川、木や石、動物などを神そのものとする考えや、山や川が神の住処であり、神によってうみだされたものとする考えがあった。

また人間は神の宿る山から魂を授かり、この世に生を受けて、死後その山へおもむき、神として鎮まるとも考えられていた。
中でも高くて形のよい山は豊かさの源と考えられ、魂の静まる地であると同時に神聖な場所として、麓のひとびとから敬われてきた。
出羽三山もまた、古くから東北を代表する聖地として多くの民衆の心をとらえ、たくさんの信仰を集めて、日本屈指の霊場として知られてきたのである。
ちなみに、中世には湯殿山を「総奥の院」(最も大切な場所)として別格化。月山・羽黒山・葉山あるいは鳥海山が「出羽三山」とされていた。
あまり歴史や信仰に興味のない人は山中や高原を行く参道は登山やハイキングコースとして楽しんでいるし、植物に興味がある人は、高山植物の宝庫として出羽三山を訪れている。
月山信仰

月山は、海抜1,984m。
半円形のアスピーデ型火山だが、これは世界でも珍しいという。
頂上の「おむろ」には月山神社があって、月読命を祀っている。
神社は水を司る農業神として、また航海漁澇の神として、広く庶民の信仰をあつめてきた。
というのも、もともと東北唯一の官幣大社で、約千年前につくられた延喜式神名帳にも載る名神大社には古い時代から朝廷も詣で、よって庶民の信仰は非常に篤いものとなっている。
山形市にある南北朝時代・貞治7年の銘のある月山結集碑は、一村百余人の登拝講中があった事を伝えており、いつの時代も篤い山岳信仰が連綿と続いてきたことをものがったっている。
月山八合目弥陀ヶ原と月山中之宮

最初の巡礼地・羽黒から車で1時間弱、海抜1400m附近に「月山八合目弥陀ヶ原」がある。
ここは、高冷地の為枯草が腐る事なく何万年となく積み重なってできた、泥炭層の湿原。小さな湖沼が散在し、あたかも神々の御田を見るようだとして訪れる人が多い。
弥陀ヶ原の中央・月山八合目の中之宮には、御田原神社がある。
ここには、須佐之男命の妻である奇稲田姫神(クシイナダヒメノカミ)が祀られ、稲田の守護神として五穀豊穣、また縁結びの神としても信仰されている。
私は、真言宗徒で、恥ずかしながら山岳信仰の信仰心は足らず、もとより三山それぞれの山の頂上など極める気迫などはない上に眠気も襲ってきたので、道の駅「月山」で仮眠をとることにした。
道の駅「月山」
道の駅「月山」は、山形自動車道の庄内あさひICから国道112号線を南東に6km、山形県南部の旧朝日村(現鶴岡市)にある。

道の駅の沿道・国道112号線は、月山を含む出羽三山の登山口に向かう道路だが、私はこの道路を反対に走って(逆走ではないw)向かう。
途中、真言宗との私としてはお寄りしないわけにはいかない、弘法大師が開山された湯殿山の総本寺「大網大日坊(真言宗 豊山派)」へ。





ここは、弘法大師自作の御本尊と即身仏「真如海上人」、国指定重要文化財「釈迦如来(金剛仏)」を安置し、徳川将軍家の祈願寺で春日局が参詣した寺として、全国に名を轟かす由緒ある寺である。


真如海上人の即身仏は、我が国でも類いまれな尊像として有名だ。
ここから道の駅へは、すぐに着く。


駐車場は、急に天気が悪くなってきたこともあるのか、客はほぼいない。

トイレは立派な建物。風格がある。

休憩環境としてはもう最高じゃないか?
敷地内、周囲ともに景観よく、しかも、天候悪化のせい、もといおかげで、人が誰もいない(笑)










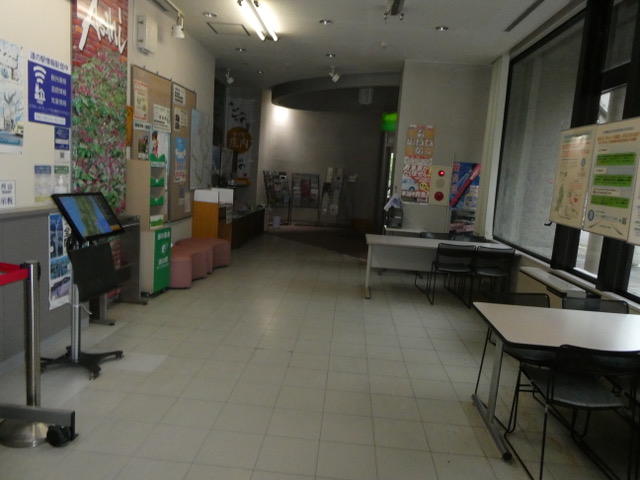

付帯施設の変遷が意味不明
さてこの道の駅「月山」は、登山口にはちょっと遠いので、「月山ワインの生産、貯蔵、販売」をメインに打ち出すべき道の駅だろう。
ところが、道の駅の付帯施設の変遷がえらいことになっている。
道の駅登録される2年前にオープンした「アマゾン自然館」は、月山とどういう関係があるのか知らんけど、アマゾンの生態系を展示していた。

もっと古くから実施されていたのは、下の写真の梵字川の川面ギリギリに飛び込むバンジージャンプだ。



バンジージャンプは1994年、旧朝日村と村民有志が任意団体を設立し、初めて開催した。つり橋から、足首にコードを巻いて約34メートル下の梵字川水面へ向けてダイビングするというものだ。
しかし2005年8月15日、バンジースタッフの男性=当時(26)=が、ゴムボートでジャンパーを回収する作業の途中、誤って川に転落して死亡するという事故が発生。運営会社は休業状態となり、そのままフェードアウトとなった。

アマゾンもバンジーも、ともに消えてしまったが、代わりに登場したのが最近流行りのボルダリング施設だ。

国際ルートセッターの平松幸祐氏が監修する初級~中級向きの28のルートに挑戦することができるというが、都市部から遠く離れたこんな山の中に、マニアックでリピーターが中心顧客になるボルダリング施設ってどうよ。
もう引退したが、私の経営コンサル感覚ではこの施設計画は怖くて進めらない。
ちゃんとマーケティングやったのだろうか?
受賞歴多数の月山ワインを販売
そんな変遷激しい付帯施設だが、やっぱり道の駅の中心となるのは月山ワインの製造、貯蔵、販売施設なのだ。

月山ワインは、旧朝日村の活性化のために1979年(昭和54年)に製造が開始された月山ワイン。 ワインの原料となる山ぶどうが村の至る所に自生していることにヒントを得た事業だが、 事業開始から数年は肝心の山ぶどうの味が安定せず、なかなか美味しいワインを作ることができなかったらしい。
その後、山ぶどう品種の改良、及び甲州ぶどう、ヤマ・ソーピニオン等の新しい品種を導入するなど努力を重ねた結果ワインの味が安定し、2017年にはジャパンワインチャレンジで最高位賞を獲得。
事業開始から45年、今では日本を代表するワインの銘柄に名を連ねるに至っている。
道の駅で販売されている月山ワインは全部で18種類ある。
ジャパンワインチャレンジで最高位を受賞した「ソレイユ・ルバン甲州シュール・リー」は720ml入りで2000円台。 日本ワインコンクール2018で金賞を受賞した「豊穣神話・甲州」は720ml入りで1400円ちょっと。ほとんどのワインが1000円台、2000円台の価格設定で、お手頃価格にての提供となっている。
ワイン販売所の横にある製造工場の中を一部、ガラス越しにだが見学することができる。
ワイン貯蔵庫は、国道112号線の旧道に設けられていた長さ400mのトンネルをうまく利用している。

ワインには詳しくないのでよくわからないが、貯蔵に最適な気温が5℃~18℃に保たれているそうだ。
年間約30万本の月山ワインが貯蔵されているというが、施設老朽化のため関係者以外は貯蔵庫の中に入ることはできなくなっていた。
