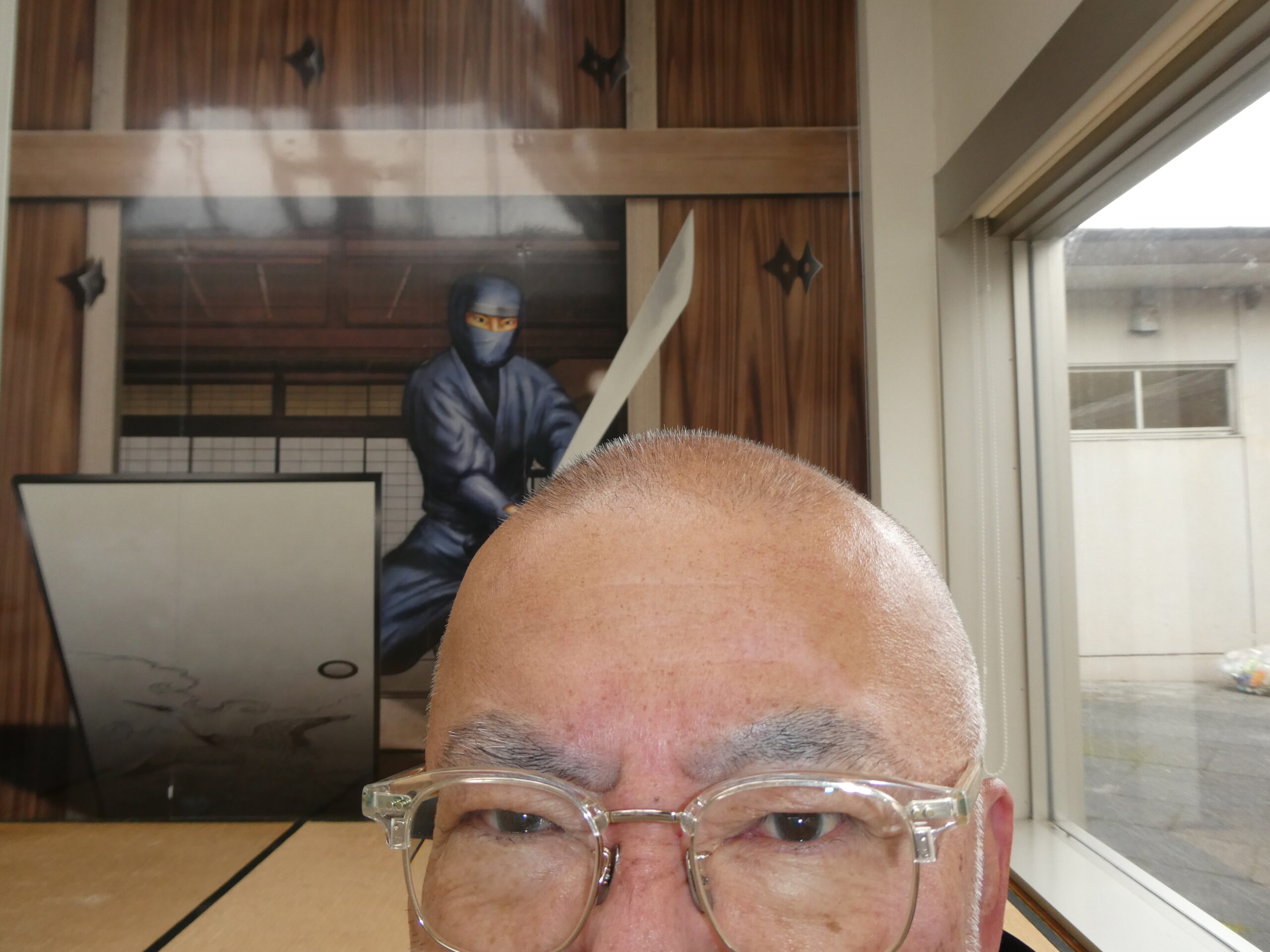
大規模な殺戮をした日本人といえば、織田信長だろう。
自分が手にかけた人数はどうだかわからないが、戦だけでなく越前や伊勢の一向一揆討伐などを含め、指示して殺させた人の数で言えば、織田信長こそはおそらく日本史上で最もたくさんの人を殺した男ではないだろうか。
そんな父親を持つ次男の信雄もまた、なんらの罪のない村人や僧侶、数万の人々を惨殺した。「天正伊賀の乱」などと言われるが、勝手に攻め込んだのは信雄。支配というものを勘違いした愚か者のひとり芝居、その挙句の大虐殺と言わざるを得ない。
天正伊賀の乱とは、伊賀国で起こった織田氏と伊賀惣国一揆との戦いの総称で、天正6年(1578年)から天正7年(1579年)の戦が第一次、天正9年(1581年)の戦が第二次とされる。
信長の次男として誕生したがのちに北畠氏の養子となって、伊勢国を支配することになった信雄は、そのどちらにも関わり、そして、信長の許しを得ずに勝手に起こした第一次では惨敗。
怒り狂った父・信長が攻めた第二次では、寺院や村々に放火、多くの人々を惨殺した。虐殺の記録としては、平楽寺(三重県伊賀市)で約700人もの僧侶を処刑。非戦闘員なのに殺害された人々は、約30,000人にのぼった。
バカ息子の大失態に我を失った信長も大したことない人間だが、信長の残虐性だけを引き継いだ信雄、本当にどうしようもない人間だった。
そもそも伊賀って?
大殺戮の舞台となった伊賀国は、現在の三重県の伊賀市と名張市にあたる。
周囲を峻険な山に囲まれた盆地で、奈良や京都と伊勢を結ぶ交通の要衝としての歴史は古い。
古代から中世にかけては奈良の東大寺などの荘園(領地)だったが、次第に土豪(その土地の豪族)や地侍(有力名主)の力が強くなり、各地に小規模な勢力が乱立するようになった。
乱立する彼らを統一する大きな勢力はなかなか現れず、小競り合いは徐々に巧妙化。情報収集やゲリラ戦を得意とする「忍者」が育っていった。
また、この地は山々に囲まれており、隠れ里としての機能もあった。
中央政権から追いやられた武士や公家たちが様々な情報をもたらし、山で修行する修験者たちとの交流からは、忍術など独特の技術が生まれた。
室町時代以降は伊賀仁木氏が伊賀守護を務めていたが、その支配力は緩く、地侍たちの自治が続いていた。
支配というものを勘違いした愚か者・信雄
こうして伊賀国には大きな勢力が登場することなく、戦国時代においても、伊賀の地侍層が在地領主権を守るために一国的規模で団結した組織をつくっていた。
彼らは隣接する甲賀郡中惣とも連携。合同会議を開くこともあった。執行部としては10人の奉行を選出するなど、甲賀郡中惣と似たやり方で組織をまとめていた。
組織化の目的は、言うまでもない、伊賀に侵入しようとする者に対する自衛である。
その頃、信雄は北畠具房の養子となっていた。永禄10年(1567)に信長は伊勢を手中に収めるべく南伊勢を支配していた北畠家を攻めたが、この際、和睦の条件として信長は次男を養子に出した。北畠家を内部から織田家の支配下に置くのがその目的だった。実際、信雄は後年に北畠具教の娘をめとり、北畠家を継ぐとともに他の北畠一族を暗殺して伊勢を掌握した。
伊勢の次は隣接する伊賀を、ということで信雄は丸山城を拠点にした伊賀攻めを企て、丸山城の修築を始めた。
それを知った百地丹波や植田光次が率いる伊賀衆はすぐさま合議を開いて対策を練り、出した結論は「完成までに攻撃すべし」。
そして無料寿福寺を拠点に、伊賀十二人衆の百田藤兵衛の率いる兵が城に対し奇襲を仕掛け、修復途上の城を焼き払う。
ここにいたり、二次にわたる「天正伊賀の乱」は幕を開けた。
第一次は信雄が完敗して信長激怒
第一次天正伊賀の乱は、織田信長の次男である織田信雄が伊賀国を攻めた戦である。
天正7年(1579)9月、信雄は約1万人の兵を率い、伊勢地口など3方から伊賀に攻め込んだ。信長には報告せず独断で実施したこの戦いは、伊賀衆の勝利に終わってしまった。
信雄の敗因は、伊賀衆のゲリラ戦についていけなかったこと。土地を知り尽くした伊賀衆による夜襲やかく乱作戦、奇襲になすすべもなく、信雄軍は敗走した。
これを知った信長はもちろん激怒する。
太田牛一による信長の生涯を記した『信長公記』によれば、信雄を「言語道断」と激しく叱責するとともに、書状で親子の縁を切る旨を伝えたとある。天下統一をめざす信長にとって、家臣、しかも次男の負け戦は威信失墜、怒るのも無理はなかった。
この頃、第三次信長包囲網の真っただ中にあって、信長は毛利氏や石山本願寺との戦いの最中。伊賀までは手が回らなかったが、天正8年(1580)に石山本願寺が陥落すると信長包囲網はほぼ瓦解。そして翌年の天正9年(1581)、いよいよ織田信長は伊賀を攻めるに至る。
第二次では信長らしい大殺戮
織田軍はなんと約4万4000人の兵を伊賀に投入。6方向から伊賀を攻め立てた。
総大将は引き続き織田信雄だったが、丹羽長秀や蒲生氏郷など織田家の主力武将も多く参加。
対する伊賀衆は植田光次や百地丹波、町井清兵衛、森田浄雲、百田藤兵衛をはじめとした伊賀惣国一揆の十二人衆を中心に約1万人余りだった。
信雄たちは伊勢に続く伊勢地口から伊賀に侵入。伊賀北部にある柘植口からは丹羽長秀や甲賀出身の滝川一益、玉滝口からは蒲生氏郷や脇坂安治、多羅尾口からは堀秀政たちが攻撃しました。さらに伊賀南西部は笠間口から筒井順慶・定次、初瀬口からは浅野長政が攻め込んだ。
伊賀衆は平楽寺や比自山城などの拠点に籠城し、夜襲などのゲリラ戦で立ち向かうが、織田軍の数にはかなわなかった。
平楽寺には約1500人の伊賀衆が籠城していたが陥落。僧侶約700人もここで斬首された。
当時の文献によれば、第二次天正伊賀の乱は織田軍による一方的な殺戮だった。織田軍は伊賀各地の神社仏閣や城砦などとともに、拠点を次々と焼き払い、約2週間で伊賀全土が焼き尽くされたという話も伝わる。
天正伊賀の乱の遺構
最終的には、信長と信雄は、非戦闘民を含め伊賀の地全人口の3分の1にあたる3万人強の人々を虐殺した。
当時をしのばせるものは石碑や郭跡などの遺構がほとんど。
伊賀衆の拠点などはすべて織田軍により焼き払われたため、現存するものはほぼない。
平楽寺の跡地には現在伊賀上野城が建ち、周囲は公園になっているが、その公園内に、寺だったころの五輪の塔や石仏だけが残されている。


また、伊賀勢最後の砦となった柏原城跡には、虎口、土塁、空堀、石落し跡などの遺構がある。




道の駅「いが」
道の駅「いが」は、三重県亀山市と奈良県天理市を繋ぐ高規格道路・名阪国道の伊賀ICから、西に200mほどの場所にある。

カーブが多い割には周りの車の走行速度が異常に早い危険な名阪国道だが、SA/PAは徐々に減っていて、ここはドライバーにとっては貴重な休憩場所の一つとなっている。
なので、駐車場は混み気味。


トイレは十分なキャパがあるので心配無用。



休憩するのにちょうどいいスペースもちゃんとある。


コンビニミックスの物産館
物産館の入口には「ニューデイリーストア」と書かれたコンビニの看板。

表向きはコンビニと言う形態をしているが、販売されている特産品の数、種類は他の道の駅と比べても遜色ない。むしろ物産館に行けばコンビニならではの弁当、総菜、飲料、日用品なども販売されているということでは大変便利。と言うのが私の感想だ。

物産館で販売されている商品は伊賀市、および周辺市町村の特産品。
伊賀名物としては「日本一硬いせんべい」として有名な「堅焼き」、伊賀忍者を彷彿させる「伊賀手裏剣クッキー」、ソフトクリームの中につぶ餡が隠れていることから命名された「忍者ソフトクリーム」など。
農産物の直売も、ちょうど良い規模感。



私の大好きな「亀山みそ焼きうどん」「一力のうなぎ志ぐれ煮」、 あさり・おかか・のり佃煮等、隣の亀山市の商品も。
「松阪牛肉味噌」「松阪牛ラーメン」「松阪牛カレー」「松阪牛サラミ」など松阪市の特産品、さらに「赤福」「伊勢うどん」「伊勢餅」「伊勢海老あられ」といった伊勢市の特産品も。



三重の郷土料理が美味しいレストラン

お腹が空いたら「お食事処 一福亭」へ。
三重県ならではの郷土料理を中心に、40種類以上のメニューから選べる。



いいなと思ったのは、「伊賀流味噌五目ラーメン」「とんてき定食」「伊賀牛入り肉吸い定食」、そして大好物の「みそ焼きうどん定食」。
もっと軽いものを、という場合にはスナックコーナーで。


