
恥ずかしながら、「富士山がいつ噴火してもおかしくない」とは知らなかった。
富士山の大規模噴火によって火山灰が首都圏に大量に降った場合の対策について令和7年3月21日に政府が初めて示した指針が報道されて初めて、その内容に驚いた次第。
富士山でおよそ300年前の「宝永噴火」に相当するような大規模な噴火が起きて大量の火山灰が噴出すると、東京や神奈川県などの広い範囲で数センチから10センチ以上積もるおそれがあり、鉄道の運行や道路の通行などに大きな影響が出るという。

人口が密集する首都圏で火山灰が積もった地域の人たちが一斉に地域の外に避難することは避難所を確保する面からも現実的ではない。ということで、30センチ未満の地域は「自宅などで生活を継続」するとし、30センチ以上積もった地域は、雨が降った際に木造住宅が倒壊するおそれがあるので避難の必要があるという。インフラは鉄道や航空機などが微量以上の降灰で運行を停止し、3センチ以上で道路通行が困難となり、物資供給は滞り始めるというのだ。
いつ噴火してもおかしくないと言うけれど…
しかし、富士山がいつ噴火するかは、予測するのがとても難しいらしい。
人がいつ風邪をひきますか?いつがんになりますか?というのと似ているらしい。そして、明日噴火するのと10年後噴火するのは、火山にとってはほぼ変わらない感覚なのだとか。人間のサイクルと富士山のサイクルは1万倍ほど違うからだ。たとえば人間の1年が火山では1万年に相当すると言うことは、火山からすると、一万年のズレがたった1年のズレ。だから、いつ起こっても不思議ではないという。
地震との違いはあるのだろうか?
地震の場合、プレートが一定の速度で動いているのでひずみが一定の速度で溜まって地震で解消するという「周期」が認められる。しかし、火山はプレートの運動によってマグマが生成されてから上がってくるまでにいろいろな過程があり、一定の周期を見い出しにくいという。
実際、富士山もこれまで10万年くらい活動しているが、10万年間同じ活動を繰り返してきたかというとそうではなく、10万年前から2万年前までは結構大きな噴火を繰り返していたが、山自体が崩れるという大きな転機があって、その後は山頂の火口から溶岩をだらだら流すような噴火をしていたが、最近2000年間は山頂の火口を使わないで、裾野に噴火口を作るようになって、現在に至っている。
一番最後の噴火は1707年、今から315年くらい前に起きた宝永大噴火だ。奈良時代〜平安時代、西暦1100年くらいまでは頻繁に噴火していたのに、そのあとの噴火で記録に残っているのはその1707年を含めて3回だけ。そして、ここ300年は噴火せず、お休みしてしまっている。なぜ300年間噴火していないのかは実はよく分かっておらず、富士山の活動の状態が新しい状態へ移り変わっている過渡期と考えられている。
このまま静かな富士山であってほしいが
残念ながら、富士山がこのまま噴火しないということはないと言う。その理由は、富士山の地下15kmほどにあるマグマ溜まりに動きがあるからだ。今は噴火に至るような大きな変化ではないが、「深部低周波地震」といって地下深部のマグマと関連して起こるとされる地震が発生していて、富士山の活動が止まっていないことは明らかなのだ。
300年間噴火していない分、次の噴火の規模は大きくなることも、統計的にはあり得ると言う。間隔が長くなると、下に溜まるマグマが多くなって、次の噴火が大きくなるというのはよくあること。実際、噴火と噴火の間の期間が長くなると比較的大きな噴火になる可能性というのは、世界の火山においての統計から否定できないという。もちろん大きな噴火に至る前に小さな噴火を繰り返すケースも考えられ、突然大きな噴火が始まるとは限らないが。
東京ドーム400杯分の火山灰をどうする?
2020年に国のワーキンググループがまとめた報告書では、富士山で「宝永噴火」に相当するような大規模な噴火が起きた場合、道路や建物などに降り積もる火山灰の量はおよそ4.9億立方メートルに達すると試算していた。これは、東日本大震災に伴う災害廃棄物量のおよそ10倍、東京ドームの400杯分に上る膨大な量である。
今回取りまとめられた政府の対応方針では、まずは、生活を続けるために必要な道路や線路に積もった灰などを優先的に取り除くとしたうえで、仮置き場の候補地も事前に決めておくことが望ましいとしていて、防災のリーダーシップを発揮するべき政府なのにまるで他人任せのような書き方で、具体的な踏み込みはまったくない。最終的な処理の方法は、再利用や資源化、土捨て場などでの処分、埋め立て、海への投入などを挙げ、複数の手段を組み合わせることが必要だとしているが、国や自治体などが連携して処理する必要があると言う当たり前のことを言っているだけである。
明日起こっても不思議ではない、想定できうる防災に対してこの国の無責任さ。
呆れるほかない。
結局、自分の身は自分で守れと言うことか
国がこんな体たらくだから、私たちは、自分の身は自分で守り、互いに助け合うほかない。
防災対策の基本は「リスクを知る」ことから始まり、具体的には私たち「自らが対策し」、そして一歩踏み込んで「ボランティア体制をとる」と言うことになる。
改めて、基本的な防災対策を確認した。まずは、住んでいる地域のリスクを調べるところからである。
住んでいるエリアのリスクを知っておく
自分の住んでいるエリアにどんなリスクがあるのかを知っておくのが基本だという。地震・津波だけではなく、洪水・浸水・土砂災害など、さまざまな災害が想定されている、そのことを改めて確認することが防災の第一歩だ。
私は兵庫県明石市に住んでいて、富士山から遠く離れた場所に家はある。最寄りの避難場所は徒歩2分で着く「高岡東小学校」。自治会役員の立場上最低限のリーダーシップ発揮も求められる。その役割を果たした上で、甚大な災害に見舞われた場合は、三木市の防災公園を拠点としたボランティア活動を想定し準備している。
家にいる時に被災すれば上記の行動をする予定だが、私は日々全国各地を車で旅しているので、実際はいつどこにいるかわからない。だから旅先ごとに国や自治体、NHKなどの報道機関が公開しているハザードマップを見て、訪問しているエリアのリスクを把握するようにしていて、その地で被災した場合の行動も想定しつつ行動している。こんな毎日を積み重ねていると、そのうちきっと日本一、日本中のハザードマップに詳しい老人になることだろう(笑)
災害時に車をどう使うかを決めておく
災害時に車をどのように使うのかは、車の有無を含め、人によって異なるだろう。当たり前だが、大雨や津波の避難に車を使うのは水没などの危険がありNG。首都直下地震発生の際は、都心部での車両の使用はNG。車で移動できないほどの災害の場合の想定も必要だ。
遠方に避難するため? 車中泊するため? 在宅避難の補助?
車の位置付けによって必然的に備えも変わってくるが、災害時、車は避難するための手段にも、避難所にもなる。特に私などは全国各地を車で旅している身ゆえ、いつどこにいるかわからない毎日の中で「防災対策」の中心は必然的に「車」と言うことになる。
と言うわけで、車を「防災活動の右腕」と位置付けている私が、「車を使った防災対策」で普段から心がけていることは大きく2つある。
【1】給油の頻度を上げること
一つ目の心がけは、ガソリンメーターが半分になったら給油することだ。
私の「防災車」の燃費からすると、ガソリン満タンで走れる距離は700キロ。その半分の350キロで給油というペースを必ず守っている。阪神淡路大震災の被災者となってから30年、車は色々乗り換えたが、私はこれを続けてきた。ガソリンがある間に応急的にできることを済ませ、ガソリンが切れて補給方法もなくなった場合のやり方を準備しておいて、長期戦への対応に繋げることが大切だと考えている。
【2】何でも密閉袋に入れておく
2つ目は、水に濡れて使えなくなるものはすべて、密封袋に入れることである。これを徹底していれば万一車が水没したとしても、水から中のものを守ることができる。充電ケーブル、LEDライト、ノートパソコン類……など、車に置くものは何でも密閉袋に入れている。
災害に備えて車の中に入れている防災グッズ
私が車に常備しているものは以下のようなものだ。
【1】ポータブル電源
私が車の助手席に置いている「ポータブルバッテリー from LEAF」は、日産自動車、JVCケンウッド、フォーアールエナジーが3社で共同開発したポータブル電源だ。その名のとおり日産のEV「リーフ」の再生バッテリーを利用しているのが特徴で、製造時の二酸化炭素の発生を抑えて、持続可能な脱炭素社会の実現に貢献するという、SDGsなプロダクトである。

「SDGs系の商品は高額」が昨今のトレンドだが、残念ながら高額だ。「ポータブルバッテリー from LEAF」もその例に漏れず、充電池容量633Whに対して価格は17万500円。はっきり言って高すぎる。
ほぼ同じ充電池容量のモデルよりも一回り大きく、重量にいたっては倍以上と言うのもダメなところだ。いくらSDGs系の商品は高額になりがちとはいえ「重たい上に電力容量が少なくて、中古のバッテリーなのに値段が高いとは……」と、私も思ったが、ではなぜこんな高額商品を買ったのか。
「動作温度範囲マイナス20~60度」と、過酷な環境に耐えられるのが本機最大のポイントだ。
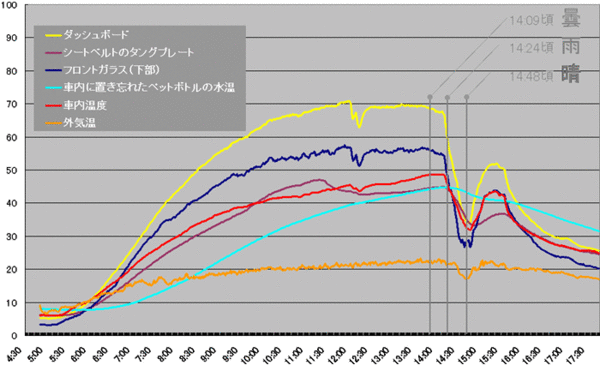
安価で新品バッテリーを搭載した製品の動作温度はマイナス10~40度と、夏場は高温になりがちな車内の環境に耐えられない。JAFが2007年4月26日に行なったユーザーテストによると、最高気温23.3度の環境下でも車内温度は48.7度にまで上昇した。つまり一般的なポータブル電源は冬以外、車内に放置できない。その冬とて、降雪地帯では動作温度範囲から外れるだろう。
「ポータブルバッテリー from LEAF」に使われるバッテリーは、本来はクルマを動かすためのもの。同程度出力の他製品より重たいのも、自動車用として堅牢に作られたためで、それが幅広い動作温度につながっている。60度は夏場で直射日光があたらない荷室、マイナス20度は冬場の寒冷地の車内を想定してつくられている。さらに自己放電が少なく、長期保管が可能というのも防災機能として優れている。私は毎日使っているので関係ないが、満充電から1年放置しても84%は残るそうだ。
充電時間はACアダプター使用時で約9.5時間、クルマのアクセサリーソケット使用時で約14時間かかるが、長期の車中泊旅行でエンジン停止時に冷蔵庫やパソコンを常時使用していても、エンジンを切る前には常にフル充電状態を確認できており、問題なく使用できている。
出力はAC100Vのアウトレット2つと、4つのUSB(Type-A×2、Type-C×2)、そしてDC100Wまで出力できる12Vアクセサリーソケットがある。
AC100V出力は合計600W(瞬間最大1200W)。HIGH-POWERというボタンを押すと900Wまで対応。電気毛布(50W)なら約12時間分の電力は取り出せるので、コールマンの厳冬対応の寝袋と組み合わせれば冬の車中泊だって大丈夫だ。
USB端子のうちType-Aは5V1.5A、Type-Cはひとつが5V3A、もうひとつが最大20V3AのPD60W出力に対応。スマートフォン(3000mAh)なら約56回、40WhのノートPCなら約15回満充電できる(もちろんエンジン停止状態で)ので、リモートワークにも完璧に対応してくれている。

【2】充電ケーブル、冷蔵庫
車内には、スマートフォン、Wi-Fi、デジカメを充電できるように3本の充電ケーブルを常備している。
充電ケーブルに限った話ではないが、災害時は運転席から身動きが取れなくなってしまう可能性もあるため、予備のケーブルも2本、運転席から手が届くダッシュボードに入れている。
そして助手席には冷蔵庫。栄養としてどうしても必要となる野菜や牛乳などを0度で保管している。

【3】LEDライト
災害時、車のガソリンやスマホの充電を温存しておきたい場面は多いだろう。そうしたときの明かり確保用にLEDライトは必須だ。車内だけでなく、車から降りて歩いて避難しなくてはならないときにも使える。LEDライトは乾電池式、ソーラー式、手回し式などさまざまな種類があるが、どれか一つではなく複数の種類を持った製品を選ぶのがポイント。どれかが使えなくなっても、他のものが使えると安心だ。災害時、特に乾電池はすぐに売り切れてしまって入手しにくくなるので、充電式のエボルタ(エネルーフ)も併用。ライト類は密閉袋に入れてダッシュボードに収納している。
【4】ブランケット(ボランティア含む)
寒いと体力を消耗してしまうため、災害時に体を保温できるものは非常に大事。冬だけでなく年中車の上の荷物ボックスに入れている。ブランケットはボランティア時の供給を想定して10枚積んでいる。
【5】非常用トイレ
食事はどうにか我慢できても、トイレだけはどうにもならない。私・神生 六(かみおむつ)は、渋滞の高速道路にて運転席で失禁した苦い体験依頼、運転時には紙おむつを着用しているが、大のための非常用トイレは必須だ。非常用トイレは薄くてコンパクトなので車上の荷物ボックスに50個載せている。
【6】水(ペットボトル2000ml)✖️40本(ボランティア含む)
ペットボトルは普段使い用に車内に最低6本は必ず置いている。日の当たらない場所、かつ運転席から取り出せるように助手席の足元に5本、助手席の冷蔵庫に1本入れているのだ。

メインとしてはボランティア活動用に、40本、車上の積載ボックスに積んである。水だけで80キロの重さがあり燃費は悪くなるが、怠っていて後悔するよりはマシだ。
車中泊旅行では、水はすべてこれを使っており、普段から使う→補充を繰り返すことで、車上保管40本の賞味期限切れも防いでいる。
【7】非常食(ボランティア含む)車上大容量Box✖️2
非常食は車内にも、車上の大容量ボックス(88リットル✖️2)にも入れている。

水と同様に「災害用」としてではなく、普段から使う・食べることで賞味期限切れを防いでいる。水や食料品を多めに買い置きしておき、古いものから消費して、消費した分を買い足す備蓄方法を「ローリングストック」と言うが、この癖がつくと、サバイバル能力は格段に違ってくる。

お茶は常温で抽出できるものを選んで楽しんでいる。
【8】防災リュック、その他サバイバル用品
自家用車所有率が高いとされる40〜50代の男性800人(全国)を対象に、防災に関する意識調査と、災害時における自動車の利用についておとなの自動車保険(セゾン自動車火災保険株式会社)が行なった調査によると。
「災害に備え、緊急用具や防災用具を車に積んでいますか?」という質問では、「とくに何も載せていない」と回答する人が全体の62.4%と最も多い結果に。その中でも、非常食や飲料水、携帯用トイレについては車に載せている人が1割にも満たない結果となっているが、せめて防災時の必携品が詰まったリュック(写真)は必須。

雪の多いエリアを旅行中に被災すれば大雪での立ち往生の可能性もあり、車のマフラーが雪でふさがってしまうと車内で一酸化炭素中毒になる危険性があるので、雪かきスコップも車に載せているし、ガソリン切れになる可能性もあるので、体を温めるカイロとエマージェンシーシート(保温シート)も積んでいる。
防災については「ちょっと心配性なくらい」がちょうど良い。災害時に「なくて困った」よりも「あったけど使わなかった」方がいいに決まっている。
私はこのように考えているし、車中泊の旅人でもあるので、車は「頼もしい防災拠点」と捉え、車中・車上にさまざまなものを常備しているのだ。

