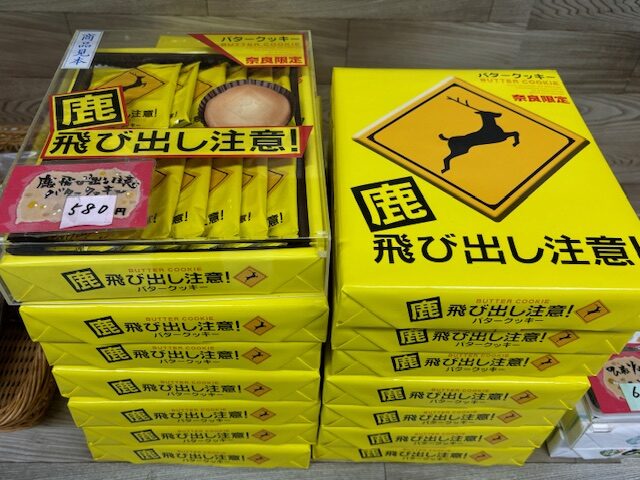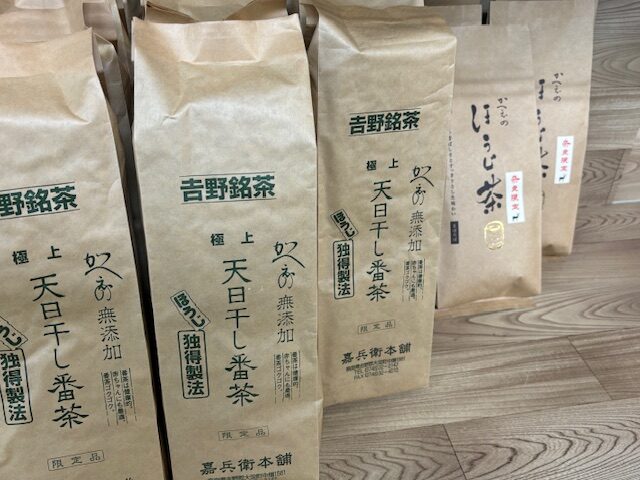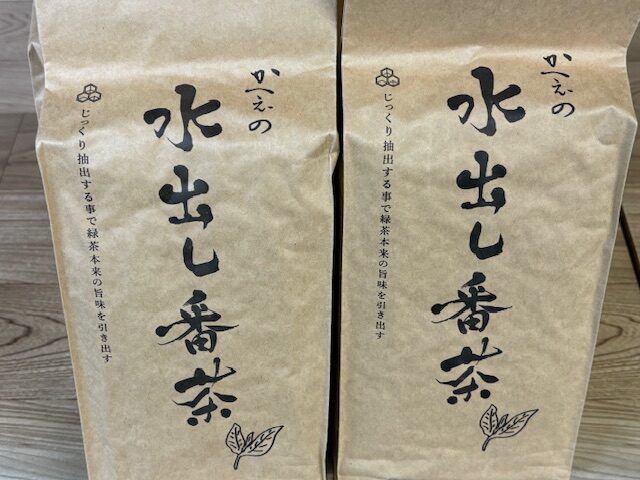大峰山は奈良県南部の山々の総称です。広義には紀伊山地の南北に連なる脊梁山脈を指し、「大峰山脈」とも呼ばれるほか、「近畿の屋根」「大和アルプス」などと謳われることがあります。また狭義には山脈の南部や、山上ヶ岳を指す場合もあるようです。歴史的には、大峰山脈のうち山上ヶ岳の南にある小篠(おざさ)から熊野までの峰々の呼び名であったそうです。対して、小篠から山上ヶ岳を含み尾根沿いに吉野川河岸までが金峰山。歴史的に使われてきた呼称および修験道の信仰では、青根ヶ峰より南を「大峯」、以北を「吉野」としてきたようです。
この一帯は1936年(昭和11年)に吉野熊野国立公園に指定され、1980年(昭和55年)にはユネスコの生物圏保護区(ユネスコエコパーク)に登録(登録名:大台ケ原・大峯山・大杉谷)。さらに2004年(平成16年)7月、ユネスコの世界遺産に「紀伊山地の霊場と参詣道」の文化的景観を示す主要な構成要素として、史跡「大峯山寺」「大峯奥駈道」ほかが登録されています。
吉野から熊野に至る大峯奥駈道は、古来の自然信仰と渾然一体となった中国渡来の神仙思想や道教、仏教の修行のために、藤原京や平城京からこの地を訪れた僧侶(修験者)によって切り開かれたことに始まり、飛鳥時代の終わり頃の文部天皇の時期に役小角によって開山されました。
熊野修験が勢力を伸ばす中で長久年間(1040年 – 1044年)に修験者(義叡、長円)により熊野から吉野までの大峯奥駈道が体系付けられたと言われています。山伏が大峯で修行することを「峯(みね)入り」「入峯(にゅうぶ)」と言い、熊野から吉野へ抜けることを「順峯」、吉野から熊野まで詣でることを「逆峯」と呼んでいて、室町時代以降は、京都などに近い吉野から入山する逆峯が多くなったそうです。また、大峯山は役小角を開祖とする修験道の根本道場とされ、俄かには信じ難いのですが、山上ヶ岳は現在でも女人禁制を守っているのだとか。

洞川から山上ヶ岳に登った深田久弥
深田久弥の随筆『日本百名山』やそれを元にした各種一覧表では、大峰山(1,915 m)とあるが、これは広義でいう大峰山の最高峰「八経ヶ岳」(八剣山)の標高である。その『日本百名山』においては、深田久弥は山麓の吉野郡天川村洞川(どろがわ)から山上ヶ岳に登っている。そして宿坊で泊まり、翌朝山頂に立つとそこから南へと大峰山脈縦走路(大峯奥駈道)に入り大普賢岳、行者還岳を経て夕方に弥山(みせん)の山小屋に着き、翌朝に近畿の最高地点である八経ヶ岳の山頂に登ったとある。縦走路はさらに南へと続くが、深田は大峰山最高峰到達に満足して山を下ったとある。
大峰山の麓・天川村には、日本三大弁財天の一つで古い歴史を持つ天河大弁財天社があり、弥山の山頂にはその奥宮がある。1984年(昭和59年)8月、大峰山寺の解体修理に伴う外陣回りの発掘調査で黄金仏2体が検出されたが、これは山岳宗教史上の大発見であった。

修験道の聖地と女人禁制
大峰山は古来、修験道が栄えてきた。開山は、修験道の開祖とされる役小角(えんのおづぬ、えんのおづの:634-706年)とされていて、山々には信仰を表す名前が付けられ、霊地や行場がいくつも残っていて、霊山と、修行場に相応しい深山幽谷を味わえる山々となっている。


中でも山上ヶ岳は、宗教的理由から女性の立ち入りを禁止してきた。「女人結界門」は実は全国に見られたもので、時が経つにつれ解除されていったが、山上ヶ岳だけは伝統を守るという理由で、現在もその制度を維持している。山上ヶ岳以外の大峰山脈の他の山岳にはもちろん女性も登っている。

そもそも古代の日本では、大きな山には魑魅魍魎(ちみもうりょう)が住んでいるため危険であると考えられ、子を産む女性の身を案じ、山に近づいてはならないとされていて、その山を修験者が修行の場に選んだことで、女人禁制が定着したのだと考えられている。
最高峰・八経ヶ岳へ
八経ヶ岳登山を日帰りでする場合、たいていは行者還トンネル西口から往復する。

そして、登山口であるその行者還トンネル西口には、深田久弥がそうしたように、山麓の吉野郡天川村洞川(どろがわ)から向かうというのが一般的だ。理由は、洞川を拠点にすれば八経ヶ岳だけでなく、山上ケ岳や稲村ケ岳など大峰の山々が目指せるからだが、今回私は大台ヶ原方面にある道の駅「吉野路 上北山」での仮眠を経て行者還トンネル西口へと向かった。
仮眠に利用したのは道の駅「吉野路 上北山」
「日本百名山」に選ばれた大台ケ原と大峯山を東西に望む上北山村は、村の総面積の97%が森林。深く険峻な山々に隔てられたわずかな土地に水田を営み、トチやカシの実を常食とする独特の食文化が育まれてきた。奈良、三重、そして和歌山にも通じ、修験道の行場となった霊峰を仰ぐ上北山村は、熊野からみて北にあたることから北山郷の異名を持つ。

また、鎌倉時代以降は争乱に敗れた貴人たちが身を寄せた地でもあり、長禄元年(1457)には三種の神器を奪還するため、赤松氏が後南朝の皇族2人を襲撃する事件も起こったため、凄惨な最期を遂げた両宮を偲ぶ史跡が村内に伝えられている。こうした激動の歴史をもつ上北山村も、今は鳥の声が響くのどかで緑豊かな村。奈良県内で2番目に広い村でありながら人口は600人にも満たない。人口密度は1平方キロメーターに2人程度で、これは全国の市町村の中で3番目に低い数字である。
つまり、上北山はどこに行っても大自然の中である。〝吉野路169〟の愛称で知られる道の駅「吉野路 上北山」は、一応、村の中心部に位置しているというが、周りには山、川、林しかない。そんな「森林村」のど真ん中を南北に切り裂くように走る国道169号沿いに本駅はある。


国道169号は奈良県南部の大動脈で、総延長は 186.0 km(三重県 11.8 km、奈良県 121.5 km、和歌山県 52.7 km)。道の駅「吉野路 上北山」から南下すればバス釣りの名所・池原ダムのある下北山村へ、また国道425号に入れば十津川村や和歌山県の尾鷲方面へ、また国道168号経由で熊野に出ることもできる。そんなアクセスの自在性を持った紀伊半島南部のドライブの格好の休憩地点であることに目をつけ、大峰山にアプローチするための仮眠拠点に選んだ次第だ。


ただ、この辺りは多雨地帯で、天気予報では近畿地方全般に晴れという予想をやはり裏切って、深夜からシトシトと雨が降り続いていた。

対岸には上北山温泉薬師湯がある。温泉はツルツルするのが特徴で、肌がきれいになり美人になると評判のアルカリ性単純温泉だ。石の湯、木の湯の二種類の内湯と、川のせせらぎと満天の星空に包まれてのんびり寛げる岩造りの露天風呂があるようだ。時間があればゆっくりくつろぐこともできたのだが、今回はちょっと寝るだけのために道の駅を利用させていただいた。
駐車場は、私好みの小さめ。


騒音に関しては、交通量が少ない夜中にたまに通行する車の音が、道路から近いためにやや気になったので、道路を隔てて向かい側にある第二駐車場も検討したのだが、そちらも騒音から逃げにくい駐車場ではあった。

トイレは駐車場のすぐそばで、便利。仮眠の前後で利用させていただいた。



出発前の利用では、ウォシュレットであったことがとても助かった。
街灯の数はそこそこあったし、私は明け方の数時間の利用だったこともあって安全面の心配はさほど感じなかった。
万一の際のコンビニは?
この施設には、デイリーヤマザキのコンビニがあるが、24時間営業ではない。

24時間営業のコンビニを調べると、なんと約45kmの位置。これはもう、ないに等しい。
コンビニが開くのを待って、朝食を買った。


コンビニだが、特産品売り場(物産館?)もちゃんとある。
物産館は上北山村の代表的な店「中谷本舗」の「ゐざさ寿司」が目玉商品(のはず)。 ただし、「ゐざさ寿司」は道の駅に置いているのではなく、注文を受けてから500メートル南にある本店から運ぶ画期的システム?であるというので笑った。物産館内で販売されている商品でツボに来たのは、「村おこし」。村民が考案した土産品というが、中身は普通の「岩おこし」である。