
今川義元ゆかりの地、そして徳川家康の居城として知られる駿府城。
「海道一の弓取り」の異名で知られる今川義元は、戦国時代に駿府城(現在の静岡市)を本拠とし、駿府城公園の一角に位置する「今川館」を居城としていた。のちに徳川家康は、家康自身が駿府城を居城とした後、今川館の跡地に駿府城を築き上げた。
往時の城郭建築の一部を復元した城と、その跡地にできている駿府城公園の桜を見に行った。
城の見学は、有名な東御門橋正面の「東御門」と、門の両脇にある「巽櫓(たつみやぐら)」から。

「東御門橋」は平成8年に復元された木橋だ。桝形虎口は、復元されたものとはいえ重厚で、気分はすっかり江戸時代。

東御門と巽櫓の中は「駿府の一生」を学べる展示室。駿府城公園内より発掘された「金箔瓦」も展示されている。
坤櫓(ひつじさるやぐら)付近に来ると、東御門周辺よりも高い石垣に囲まれたように感じる。東側よりも西側の標高が高いかららしい。より高い所から敵に攻撃されることを想定し、駿府城は西側の守りを手厚くしていた。その工夫の1つが「石落とし」だ。

石を落とされる側から見上げると、かつての攻防を想像するだに恐ろしい。

今川義元と武田信玄と徳川家康
今から650年以上前の室町時代のこと。今川範国(のりくに)が駿河国の守護に任ぜられた。駿府城周辺に今川氏の館があったのは、そのころからと考えられている。
今川氏全盛期9代義元の時代に、のちに天下人となり江戸幕府を開いた徳川家康(幼名 松平竹千代)は人質として19歳までの12年間を駿府で生活。この時期に臨済寺の住職太原雪斎などから種々の教えを受け、人間形成の上で非常に重要な時期となったことはあまりにも有名だ。
戦国争乱の中、永禄11年(1568)、10代今川氏真は甲斐の武田信玄に攻められて掛川に落ちたが、このとき駿府の町は焼き払われている。さらに天正10年(1582)に家康が駿府の武田勢を攻めたが、再度の戦火によって、中世駿府の町はほぼ壊滅状態となった。
豊臣秀吉と徳川家康
駿河国を領国の一つとした家康は、天正13年(1585)から自らの居城とすべく駿府城の築城を始め、天正17年(1589)に完成させる(現在の二ノ丸以内の部分)。しかし、待ちに待った居城完成の翌年、家康は関白豊臣秀吉の命によって関東に移封(国替え)され、駿府城主は豊臣系の家臣中村一氏(なかむらかずうじ)となった。
私が昔いたリクルートという会社は、社員がマンションを買うと「安住を考えるな」とばかり敢えて遠くに異動させられたものだが、家康はさぞややるせなかったことだろう。
豊臣秀吉亡き後、関ヶ原の戦いなどで豊臣系を叩き潰して怨念を晴らした?家康は、慶長8年(1603)征夷大将軍に任ぜられ江戸幕府を開く。
江戸を凌ぐ黄金時代へ
慶長10年(1605)将軍職を2代秀忠に譲った家康はその翌年、駿府を「大御所政治」の拠点の地と定めて再び戻ってくる。
家康は、秀吉の命によって安住を許されなかった天正期の駿府城を拡張(三ノ丸)修築し、駿府の町割りや安倍川の治水事業を推し進めた。現在の静岡市の市街地の原型は、このとき形作られていったのである。
そして、家康自らは、晩年も「大御所」として天下の実権を掌握し、駿府は江戸をも凌ぐ政治・経済・文化の中心として黄金時代を迎えたのだった。
完成してるのに通れない馬路(まじ)トンネル、まじか?
全くの余談だが、静岡県の山奥から駿府に向かう途中に、完成から20年が経過しているにもかかわらず、いまだ通れないトンネルがあった。

本川根~静岡を結ぶバイパスの途中にある馬路(まじ)トンネルだ。
大井川鐵道の千頭駅付近から静岡市へ国道362号を進んでいくと、馬路大橋を渡った先にこのトンネルが見えてきた。しかし入口は車止めで封鎖されているため、先へ向かうには、トンネル手前から右へ延びる細い現道を進んでいくしかない。まじか!
だって、馬路トンネルの銘板には「延長292m」、完成は「2003年6月」と記されている。完成からすでに20年経過しているではないか。
後でその理由を調べたら、全長1.6kmのうち1.3kmは整備済みで、現在は残り0.3kmの区間で工事が続いているらしく、長さ220mの橋が架かれば通れるようになるとのこと。開通は2026年度の見込みだそうな。今度は予定通り行ってほしい、まじで。
全国唯一、3箇所に分散する道の駅
東西に長い静岡県のほぼ中央部にある駿府城。ここにもっとも近い道の駅となると、「宇津ケ谷峠」しかない。
かつては東海道の交通の要所とされ、現在は主要国道1号線が走る宇津ノ谷峠だが、道の駅は東側(静岡市駿河区)に2箇所、西側(藤枝市岡部町)に1箇所、 計3箇所に分散。しかも各々の施設は小規模で、3つ合わせても一般的な道の駅より小さいぐらいである。
しかしながら周辺の交通量は非常に多く、パーキングエリアとして、ドライバーの休憩に大いに活用されている。
ということで駐車場には結構な数の車が。トラックの比率も高い。


トイレこそ、道の駅でもっとも有難い存在であるということを改めて感じる。清掃してくださる人に感謝!



この道の駅では、休憩環境もかくあるべしと痛感。ドライバーが体を休めるという道の駅の原点がここにある。







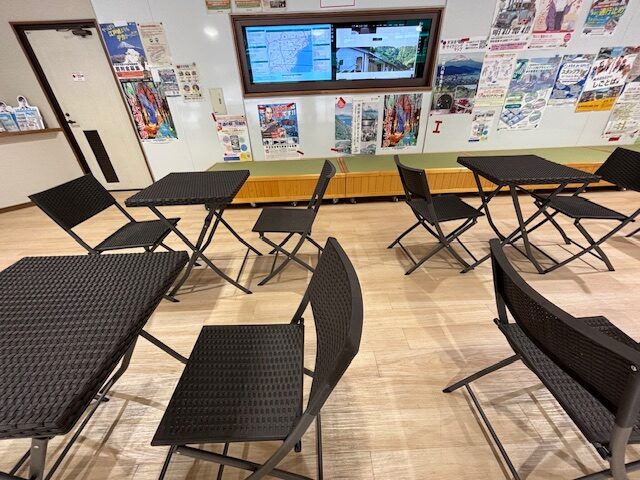

小さな施設内に特徴ある商品が多数
東側の下り線の施設では、茶処静岡ということもあって川根茶、めかぶ茶が。田丸屋のわさび漬けや安倍川もちなどは土産品に最適だろう。
お茶に付いてだが、西側上り線の施設では岡部茶がメイン。東は川根茶、西は岡部茶と、推しが違っていた。




「増量フェア」の文言に後押しされて、真っ赤なトマトを購入。
東西で名物も異なるレストラン
東側下り線のレストランでは「生姜焼き定食」「あじのほぐし身丼」「天丼」「宇津ノ谷カレー」など。西側上り線では「宇津ノ谷そば」「宇津ノ谷うどん」が名物だ。
私はおでんをいただいたが、これは実に美味かった!



